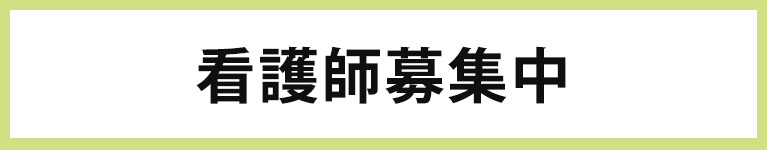食道、胃の疾患
逆流性食道炎

胃酸や胃の内容物が食道に逆流することで、胸やけや呑酸などの症状を呈する疾患です。食道には粘膜の保護機能がないため、胃酸に触れると食道粘膜に炎症を起こすことがあります。心疾患がなく、胸やけやみぞおちの痛み、咳などの症状がある場合、逆流性食道炎の可能性が高いと言えます。内服薬で症状を緩和できますが、生活習慣によって発症するため再発しやすい傾向があります。再発を繰り返して食道の炎症が長期に及ぶと食道がん発症リスクが上昇してしまうため、受診してしっかり治し、再発を防ぐことが重要です。
食道カンジダ症(カンジダ性食道炎)
食道カンジダ症は、カンジダと呼ばれる真菌が食道に感染し、炎症を引き起こすことで起こります。カンジダは通常、健康な人の体内にも存在していますが、免疫力の低下や抗生物質の使用などによって増殖し、感染症を引き起こすことがあります。食道カンジダ症の症状には、のどの違和感や痛み、食物がつかえる感じ、口内の白い斑点や乾燥感などがあります。診断は内視鏡検査によって行われ、食道の粘膜上にカンジダの発育が確認されます。
食道がん
早期の食道がんは、ほぼ自覚症状はなく、進行がんになると食道の管腔が腫瘍で塞がれるため、胸がつかえるような症状が出現します。食道がんは、早期からリンパ節や他臓器に転移しやすいため、胃カメラ検査で早期発見し、早期治療するのが大切です。飲酒や喫煙をする方は、症状の有無にかかわらず一度は胃カメラ検査を受け、その後は定期的に検査することをお勧め致します。(わずかな飲酒で顔が赤くなる方は、発がんリスクが高くなることが知られています。)
胃がん
胃がんは胃の表面から発生し、進行するにしたがって粘膜の深部に広がっていきます。早期胃がんの状態で発見できれば、外科手術ではなく内視鏡手術で完治できる可能性があります。しかし、早期胃がんは基本的に自覚症状が無く、進行癌でも症状がないことも多くあります。症状の有無にかかわらず一度は胃カメラ検査を受け、その後は定期的に検査することをお勧め致します。
胃炎、ピロリ菌
胃炎は、胃粘膜が炎症を起こしている状態です。一時的に炎症を起こした状態を急性胃炎と言い、長く炎症が続いている状態を慢性胃炎と言います。急性胃炎の原因は、主に暴飲暴食・過度の飲酒・喫煙・ストレスなどとされています。また、慢性胃炎の原因は、主にピロリ菌感染とされます。ピロリ菌に感染している場合、胃粘膜の炎症が長期にわたり続くことで胃がんや胃潰瘍などが発生するリスクが高まっていきます。ピロリ菌の除菌治療を行い、予防することが重要です。
アニサキス

アニサキスは寄生虫の一種で、サバやアジ、イカなどの魚介類を生で食べることで人の胃に感染します。原因となる魚介類を食べた数時間後に突然、みぞおちの辺りに激しい腹痛が出現し、吐き気などの強い症状が出現します。治療は胃カメラ検査で胃壁に感染しているアニサキスを取り除きます。
胃潰瘍、十二指腸潰瘍
ピロリ菌感染やNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)と呼ばれる痛み止めの常用などが原因で胃や十二指腸の粘膜に傷がつき潰瘍になります。みぞおちの辺りの鈍い痛みや腹部膨満感などの症状が出現しますが、約50%は無症状と言われています。ひどくなると、潰瘍が深くなって、出血したり穴が開いたりする場合もあります。症状の有無にかかわらず一度は胃カメラ検査を受け、ピロリ菌の有無を調べておくことをお勧め致します。
機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシアとは胃もたれやみぞおちの痛みやもたれ、満腹感やしゃくねつ感などのつらい症状を繰り返し感じることがあるのに、胃カメラや超音波検査などで検査をしても胃の異常が見つからず、胃や十二指腸の機能的な問題によって症状が引き起こされている病気です。ストレスと関連があり、QOL(生活の質)に影響するため、我慢せずに適切な治療を受けることが大切です。
食道・胃静脈瘤
ウイルス性肝炎などの肝障害が進行し肝硬変になると、食道や胃の静脈が風船の様に膨らみ食道・胃静脈瘤を形成することがあります。食道・胃静脈瘤自体の症状はありませんが、破裂すると大量出血をきたし致死的になる可能性があるため、ウイルス性肝炎などの肝障害がある方は定期的に胃カメラ検査を受ける必要があります。
大腸の疾患
大腸がん、大腸ポリープ

ほとんどの大腸がんは大腸ポリープが放置されたものから発生します。粘膜表面にとどまっている早期大腸がんは内視鏡で切除することができ、完治が望めます。また、ポリープを切除することは将来の大腸がん予防になります。早期がんは症状に乏しく、進行するに従い便秘、血便、便が細いなどの症状が出てきます。大腸がんは近年増え続けていますので、発症リスクが上昇しはじめる40歳になったら症状がなくても内視鏡検査を受けることをお勧めしています。
便潜血陽性
一般的な健康診断では、大腸がんの検査項目として便潜血検査(検便)を行います。便潜血検査は、便に含まれる微量の血液成分の有無を調べます。痔などの肛門部からの出血で陽性になることも多いですが、進行性の大腸がんの方の場合は約80%が陽性になる検査です。便潜血検査陽性となった方のうち、約30%に大腸ポリープが発見されるため、大腸疾患の早期発見のきっかけとして有効です。便潜血検査が陽性となった場合は、大腸がんがないか調べるために、大腸カメラ検査をお受け頂く必要があります。
過敏性腸症候群
ストレスや不安などが原因となって発症する消化管の機能性障害です。腸管の知覚過敏などが原因となり、長期間続く腹痛や腹部不快感、繰り返す下痢や便秘などの症状を認めます。
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)
炎症性腸疾患はinflammatory bowel disease(IBD)と呼ばれ、主に潰瘍性大腸炎とクローン病のふたつが代表的です。残念ながら一度罹患すると長期にわたって病気と付き合わなければなりません。そのなかでも状態が悪い時期(活動期)と比較的落ち着いている時期(寛解期)があります。原因はまだはっきりとは分かっておりませんが、遺伝や環境、腸内細菌の異常などの要因がさまざまに関わり、免疫異常が起こり発生すると考えられております。若い方に発生することが多く、下痢、血便、腹痛、体重減少、発熱などの症状がみられます。
虚血性腸炎
虚血性大腸炎は大腸の血流が一時的または部分的に減少することで、大腸の壁が障害を受け、腹痛や血便などが現れる病気です。この疾患は主に中高年の女性に多く見られますが、年齢や性別を問わず発症する可能性があります。腸の壁が障害を受けた深さによって軽症型と重症型に分けられます。軽症型は自然に回復する場合が多いですが、重症型では腸の壊死や穿孔(穴が開く状態)を引き起こし、緊急手術が必要になることがあります。
感染性腸炎
細菌性とウイルス性の腸炎がありますが、ほとんどは抗生剤を必要とせず自然軽快します。下痢に関しては下痢止めをもちいると菌の排出を遅らせて長引かせる可能性があるため推奨されていません。一番の問題となるのは脱水になることですので、飲水が可能な方はしっかりと水分を確保しておき、水分摂取をしっかり行うことが大切です。吐き気が強すぎて飲水が取れない方や、ご高齢の方で十分飲水が取れないような場合は点滴で脱水補正をする必要があり、入院適応となることもあります。
ノロウイルス感染症

ノロウイルスは嘔吐、下痢、腹痛といった急性胃腸炎の症状を引き起こすウイルスです。特に冬季に発症が多く、注意が必要です。当院ではノロウイルスの迅速診断を行っております。嘔吐および下痢の症状のある方、食品関係のお仕事の方、医療関係、介護関係のお仕事の方で心配の方はお気軽にご来院下さい。